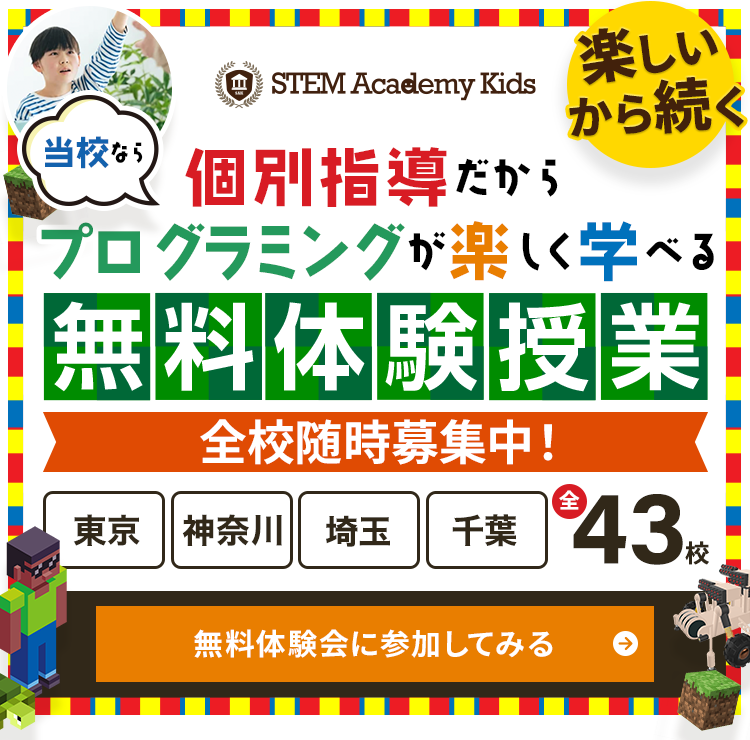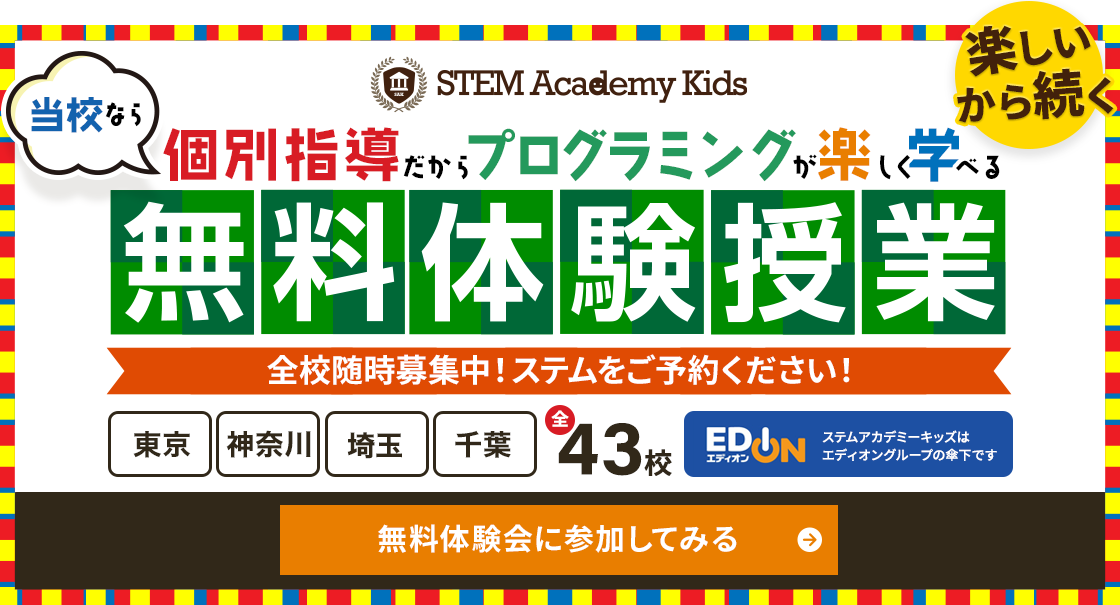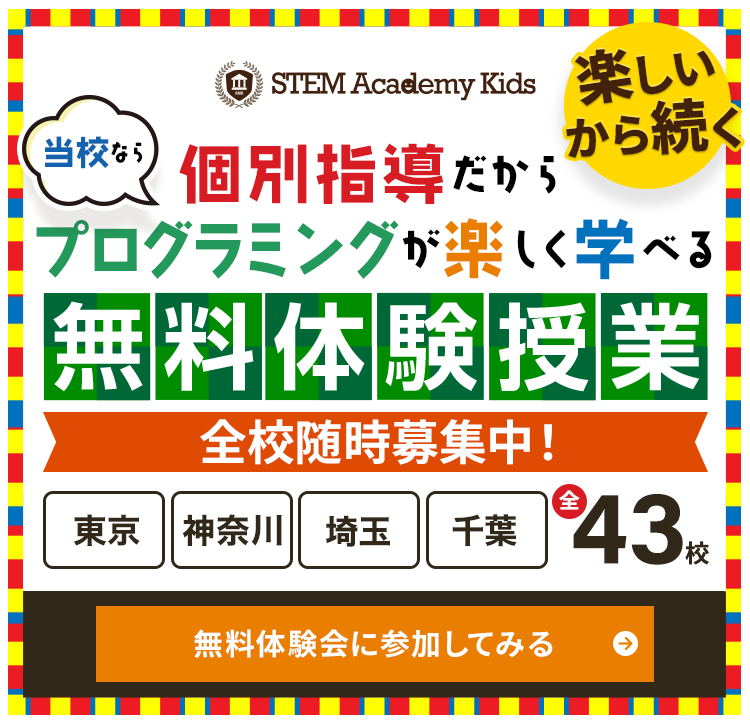季節の変化を予測するプログラム:春はどうやって「見える化」できる?
雨が降ったりやんだり、寒暖差の激しい日が続いていますね。まさに「三寒四温」という言葉がぴったりの季節。こうした変化の中にも、少しずつ春の気配が感じられるようになってきました。
でも、こうした“春の気配”、もしデータやプログラムを使って「見える化」できたらどうでしょう?
自然の変化を「感じる」だけでなく、「読み解く」ことができるようになると、身の回りの季節がぐっと面白く見えてきます。
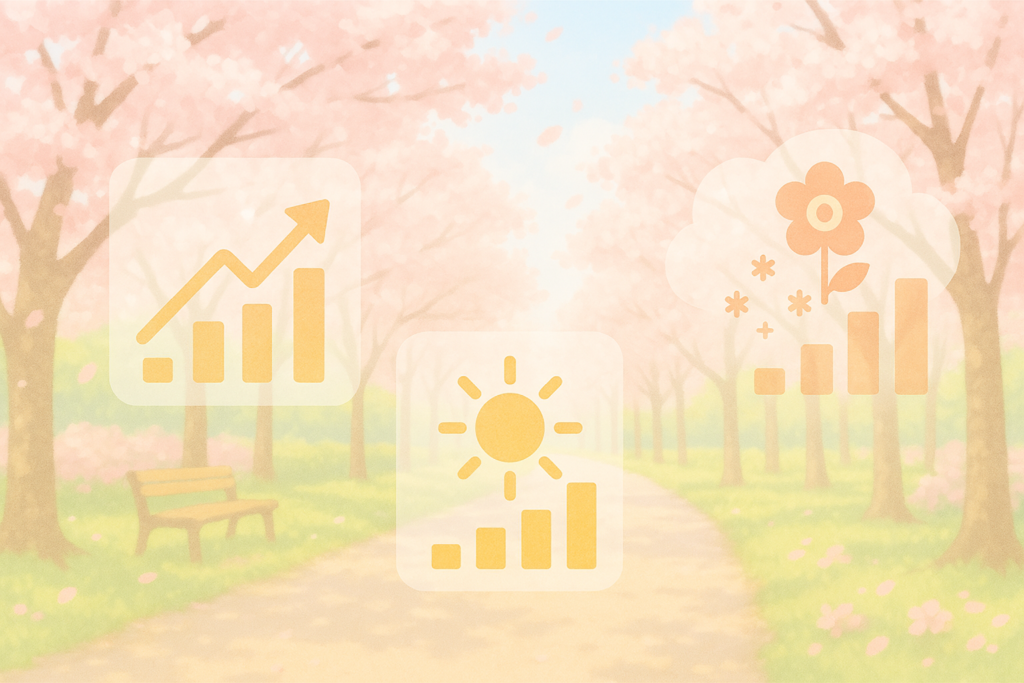
春は「データの積み重ね」でできている?
春が来るといっても、急に世界が変わるわけではありません。実は春の訪れには、
・平均気温の上昇
・日照時間の変化
・花粉の飛散量
・植物の芽吹きや桜の開花日など、さまざまな要素が少しずつ変化しながら影響しています。
こうした情報は、インターネット上で多くの機関(気象庁など)から公開されていて、実際にデータとして見ることができるんです。
「今日は暖かいな」と感じたその日の気温、「そろそろ桜が咲きそう」と思ったタイミング――それらは、ちゃんとデータにも表れているんです。
プログラムで“春”を見える化してみよう!
Scratchなどのプログラミングツールを使えば、こうした季節のデータをもとに、 自分だけの“春を知らせるプログラム”を作ることもできます!
たとえば…
・気温の変化をグラフにする → 数値が上がっていく様子が目に見えてわかる!
・日ごとに変わる「桜の開花予想カウントダウン」 → 日数と気温を使って、桜の開花をアニメーションで表現
・花粉情報をキャラクターが教えてくれるアニメーション → 「今日は花粉多め!マスクを忘れずに!」とお知らせする作品
難しいデータ処理じゃなくても、「今日は何度?」「何日たった?」などの情報を使ってアクションを起こすだけで、立派な“春の見える化”になります。
季節の変化に気づく力=プログラム的思考
「春を見える化する」ことは、プログラミングのテクニックを学ぶだけではありません。
日々の変化に目を向けて、
・「なぜ変わったのか」
・「何が関係しているのか」
・「次はどうなるのか」
と考えることは、まさに「プログラム的思考(ロジカルシンキング)」につながります。
自然の“なんとなく”を、「理由」と「パターン」にして読み解く。
これができるようになると、日々の景色がちょっとだけ違って見えてきます。
自然を感じて、論理でとらえる楽しさを
自然の変化をデータで見てみると、「春ってこうやってやってくるんだな」と少しだけ先回りして感じられるのが面白いところ。
感覚で楽しむ春も素敵ですが、そこに“プログラムの視点”を加えてみると、世界がちょっと広がって見えるかもしれません。
春の変化に目を向けながら、「これってどうなってるんだろう?」という疑問を、ぜひご家庭でも楽しんでみてくださいね。
感じる × つくる × 考える——そんな体験が、未来の学びの種になるかもしれません